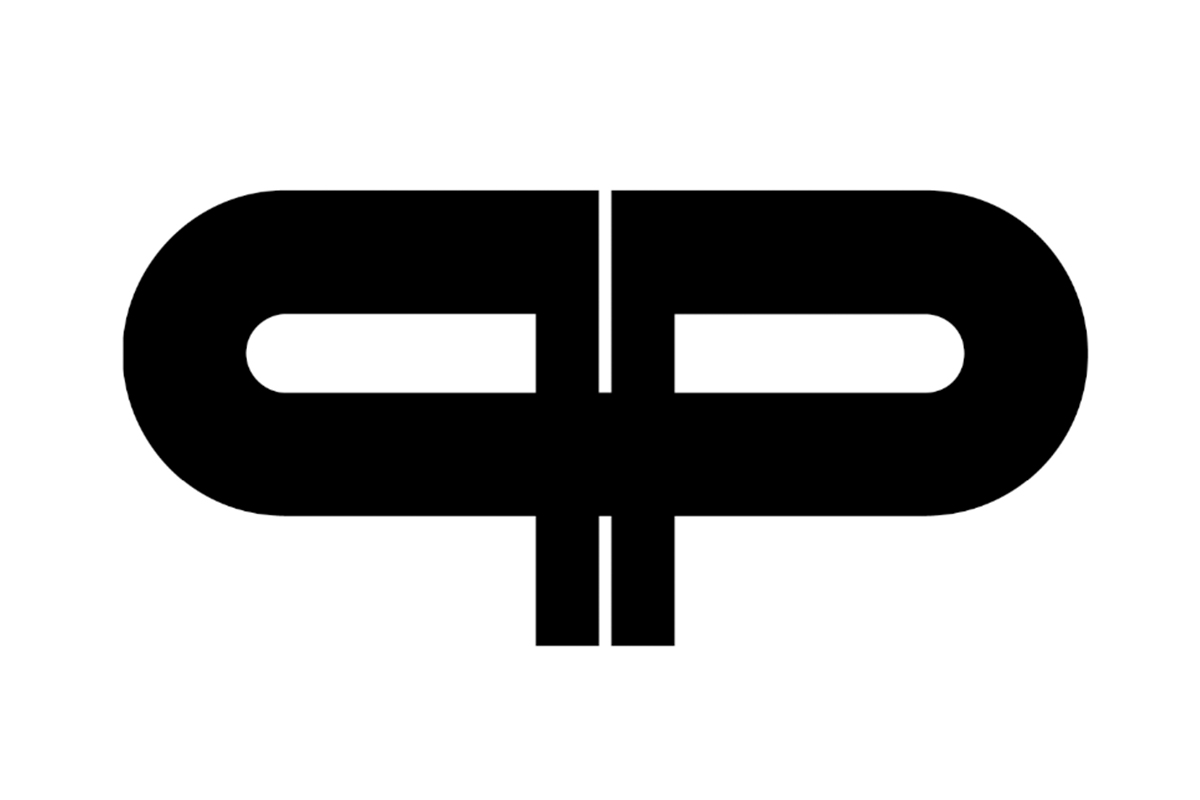ウェグナーとPPモブラー、理想を共有した二つの手
1950年代のデンマーク。家具デザインが世界的に注目され始めた時代に、ハンス・J・ウェグナーとPPモブラーは出会いました。
デザイナーと職人という立場を越え、互いの信念を共有しながら歩んだ二人の関係は、やがて「理想を形にする協働」として結実します。
ウェグナーは、見た目の美しさだけでなく、使う人が自然に心地よさを感じられる椅子を求め続けました。
一方のPPモブラーは、木という素材を徹底的に理解し、精密な加工と手仕事でその理想に応えました。
二人の出会いは、デンマーク家具の歴史の中でも特別な意味を持ち、今日まで続くクラフトマンシップの原点となりました。
ウェグナーとPPモブラーの出会い
ウェグナーは、家具の形だけでなく「座る体験」そのものを大切にしたデザイナーでした。
彼の作品には、人の体の動きに寄り添うようなやさしさと、木のぬくもりを引き出す技術が共存しています。
1953年、キャビネットメーカーで修業を終えたばかりのラース・ペダーセンとアイナー・ペダーセン兄弟がPPモブラーを設立しました。
二人は、素材の性質を見極めながら新しい構造を試すことを得意としており、その姿勢が後にウェグナーとの理想的な関係を築くことになります。
協働の始まり — 信頼を生んだ下請け時代
ウェグナーとPPモブラーの関係は、「パパベアチェア(PP19)」のフレーム製作から始まりました。
当時、PPモブラーはAPストーレンの下請けとして参加していましたが、目に見えない部分まで丁寧に仕上げる姿勢が、ウェグナーに強い印象を与えました。
「見えないところこそ美しく」。
その信念を共有した二人の間に、確かな信頼が生まれます。
1969年には、PPモブラーが自社名義で初めて手がけたウェグナー作品「PP203」が完成し、協働は正式なパートナーシップへと発展しました。
レガシーの継承 — 品質を受け継ぐ工房として
1970年代に入ると、かつてウェグナーの椅子を製作していた名工房が次々と姿を消していきました。
そんな中でPPモブラーは、ウェグナーの代表作の製造を引き継ぎ、「品質を守る工房」としてその名を確立します。
「ザ・チェア(PP501/503)」や「パパベアチェア(PP19)」など、歴史的な名作を現代の技術で再現し、当時と変わらぬ精度と美しさを保ち続けています。
また、1978年に製作された「PP52/62 フェリーチェア」は、北海で漂流しても壊れなかったという逸話が残っており、PPモブラーの高い技術力を象徴しています。
ウェグナーの思想とPPモブラーの職人技は、今も一体となって受け継がれています。
技術の進化 — 伝統と革新の融合
PPモブラーの工房では、伝統的な木工技術を守りながらも、常に新しい技術を積極的に取り入れてきました。
2001年に導入されたCNCマシン(精密切削機)は、複雑な接合部を極めて高い精度で加工できるようにしました。
ウェグナー自身もこの機械を見て、「これがあればもっと理想を形にできた」と感嘆したと伝えられています。
さらに、1986年に完成した「サークルチェア(PP130)」では、航空機技術を応用したラミネート成形が使われています。
薄く削った木材を重ねて曲げることで、軽さと強度を両立させるという革新的な手法でした。
伝統と最先端技術の融合こそ、PPモブラーが今も追求し続けるクラフトの理想です。
未来への継承 — 職人の手から次の世代へ
現在、PPモブラーは創業者の孫であるキャスパー・ホルスト・ペダーセンが三代目として工房を率いています。
彼は、祖父たちの哲学を守りながらも、環境への責任を重視する新しい時代のものづくりを進めています。
植林活動「PPの森」や、環境に配慮した仕上げ材への転換など、工房の活動はウェグナーが大切にした「人と自然の調和」の理念と重なります。
また、ウェグナーの娘であり建築家のマリアンネ・ウェグナーは、「PPモブラーは父の理想を最も正確に形にできる工房」と語っています。
ウェグナーとPPモブラー。
二つの手が重なり合って生み出した椅子は、今も静かに「ものづくりの誠実さ」を語り続けています。
(展示情報)
織田コレクション ハンス・ウェグナー展 ─ 至高のクラフツマンシップ
会期:2025年12月2日(火)〜2026年1月18日(日)
会場:渋谷ヒカリエ9F ヒカリエホール
公式サイト:bunkamura
関連記事:PP Møbler | PPモブラー